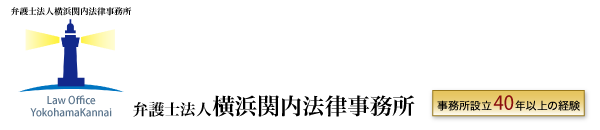借地借家
借地借家に関する問題とはおおざっぱにいえば、土地や家を貸し(借り)ていることにまつわり生じる問題といえます。例えば、「借主が家賃や地代を払ってくれない」とか、「家主に突然出て行って欲しいと言われた」などの、いわば本当に「問題」として生じる事柄から、単に時期が来て契約を更新する場合の対応などの事柄も含まれます。
家賃や地代が支払われない場合は、それに基づいて契約を解除し、借主を立ち退かせ、不払いになった賃料の支払請求をすること等を、最終的に裁判で行う必要が出てきますし、また、家主に突然出て行って欲しいと言われた場合で、契約期間内の解約ができると契約書の中で定めていたとしても、通常これは無効と扱われるなど、借地借家の関係は簡単そうですが意外と難しい問題がある場合もあります。
家や土地を借りる人の権利は、借地借家法や旧借地法といった法律によって保護されています。
特に借地権は土地の価格の6~7割程度の価格で取引をされる財産的価値の高い権利として扱われ、取引をする際には地主の承諾やそれを受けるために承諾料が必要となることがほとんどです。
借家権についても、解約や立ち退きをする際に、いわゆる立退料が発生する場合があるなど、やはりその権利は保護されており、これらの借主の財産権と、貸主の土地や建物の所有権を調整する問題が借地借家の問題といえます。
~借地非訟手続~
借地契約をしていますと、建物の増改築、建替えをしたいという場合が出てきます。この中には、木造建物を鉄筋コンクリート造りにしたいというケースもあるでしょう。さらには、借地権そのものを建物ごと売却したいという場合、借地権を転貸したいという場合も出てきます。こうした場合、借地契約書をみると、大概、増改築禁止条項が入っていたり、建築建物については、木造普通建物に限定されていたり、又借地権の譲渡、転貸の禁止が謳われていることに気付かれると思います。
しかし、長年使っている家ですから、増改築や、条件変更の必要性が出てくることは避けられないことです。又、借地権の譲渡・転貸の必要性が生じてくることも不合理だとはいえません。そこで通常、こうした契約条項があったとしても地主側と協議をして増改築やら、借地権の譲渡転貸を実現しているわけです。
こうした協議については、地主側に一定の承諾料という名目で金銭の支払いがなされるのが普通です。ところが中には、何が何でも反対だ、契約は守ってもらいたいなどと言って全く協議に応じようとしない地主、あるいは極めて高額な承諾料を主張する地主も出てきます。相応な協議により合理的に決まればよいのですが、こうしたことが期待できない場合、裁判所が地主に代わって承諾手続きをする制度が借地非訟と呼ばれる手続きです。裁判所はこうした場合、合理的な地主に対する承諾料を定めて、増改築や、借地権の譲渡、転貸を認めてくれますので、利用価値の高い制度といえます。
交通事故
交通事故が起きた場合、加害者が追わなければならない責任は、1)民事上の責任、2)刑事上の責任、3)行政処分の三つがあります。このうち、民事上の責任としては、民法709条(不法行為)に基づく損害賠償責任と、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を負うことになります。
この場合に加害者が賠償すべき損害は、大まかに分けると、①相手方の人損(治療費、逸失利益、慰謝料など)、②車輌の修繕費等の物損がありますが、交通事故は非常に件数が多いため、過去の裁判例の集積を基に、それぞれの損害賠償額について一定の基準が存在します。
主なものとしては、東京三弁護士会日弁連交通事故相談センター東京支部による「損害賠償算定基準」(通称赤本)と、財団法人日弁連交通事故相談センターによる「交通事故損害額算定基準」(通称青本)です。
交通事故は、日常の中で起こりやすいものなので、加害者になる可能性も被害者になる可能性もありますが、そのような場合には、これらの基準を基に、どの程度の賠償を行うべきなのかの判断の目安にすると良いでしょう。
尚、自動車運転者は、自賠法により自賠責保険に加入が義務づけらており、さらに加えて任意自動車保険に加入することもできますので、交通事故の被害者は、加害者が加入している保険会社に対して損害賠償を請求することが多いと思われます。
この場合、気を付けなければならないのは、自賠責保険は人身事故の損害の填補しかしないので、対物事故の損害については、任意保険に加入していなければ填補されないということです。
また、保険会社が設けている損害賠償基準は、前述の赤本や青本といった過去の裁判例の集積による基準よりも低くなっていますので、保険会社の担当者と示談交渉をする場合には、その基準が妥当かどうかを一度弁護士等に相談する必要があると言えます。
そして、刑事上の責任を負う場合は、人身に対する死傷事故を起した場合で、そのような場合には、業務上過失致死傷罪に問われますので、弁護士に刑事弁護を依頼する必要が生じるでしょう。
最後に、行政上の責任を負う場合には、運転免許の取消や、免許停止処分などを受けることとなり、この処分を行うのは管轄地の公安委員会となっていますが、処分に不服がある場合にはその旨の主張をする必要がありますので、弁護士に相談をするとよいでしょう。
医療過誤
医療過誤とは、医療機関側(医師、看護師等)の過失による診断・治療行為上の過誤のことです。医療過誤による医師あるいは病院の責任は、診療契約に基づく債務不履行責任、あるいは不法行為責任を根拠として損害賠償請求をすることにより、問うことができます。債務不履行責任を問う場合には、医師(病院)側が、責めに帰すべき事由がなかったことを立証しなければなりませんが、不法行為責任を問う場合には、被害者(患者)側が、医師の過失を立証しなければなりません。
医師の過失を問う場合には、その根拠となる資料のほとんどがカルテや診療記録類なので、通常は、証拠保全という裁判所への申立手続によって、病院側にある記録内容を保全して確認する必要があります。
これにより入手できた資料と、被害者(患者)側の資料や説明から、医師(病院)側に過失があったのか否か、あったとすればどのような過失があったと推測できるのかをある程度見極めて、交渉ないしは訴訟等に踏み出します。
しかしながら、医療過誤は、専門的な医療行為上の過誤の問題であるため、専門外の弁護士や裁判官がその内容を理解するためには、多くの文献や医師の意見を採り入れる必要があり、訴訟を提起した後も最終的な結論が出るまで長期にわたることになる場合が多いと言えます。
損害賠償請求
損害賠償請求が出来る事案は大別すると二通りあります。第1は、債務不履行に基づくもの、第2は不法行為によるものです。又、特別なものとして、損害賠償の法定義務が商法、その他特別法などに定められておりこれに基づき賠償義務が認められるものもあります。
ところで、債務不履行というのは、簡単に言えば、当事者の間に交わされた約束(契約)に違反することです。約束に違反して相手に思わぬ損害をかけてしまえば、その損害を回復するのに必要な金銭的な補償をしなければならないというのは当然のことだと言えますが、実際には、故意過失がないとか、相手にも相応の責任があるとか、損害額の金額がおかしいなど様々な点で争われることが多いのも事実です。
又、不法行為というのは、契約その他特別な約束がない場合でも、およそ違法な行為を働いて相手に損害をかけた場合は金銭補償をすべきだというものです。自動車事故などがその適例でしょう。
このような損害賠償請求は一般民事事件の代表的なものですが、その内容は多種、多様にわたりますので、実際に損害賠償請求する場合には、どの様な状況の基にどの様な不利益が発生したかつぶさに検討することが必要になります。
そしてこうした損害賠償を請求する場合、相手方の支払能力、保険の存在なども検討すべき重要な事項となります。
消費者事件(製造物責任を含む)
~消費者事件~従来から一般個人の消費者が契約取引をする中で、キャッチセールス、マルチ商法、霊感商法、先物取引などにより様々な被害を被ることが多くありました。勿論、このような場合、民法上詐欺取消権や契約解除権等の行使を通じて、被害回復を図る事も可能でしたが、消費者と事業者との間には絶対的な情報保有量・交渉力の差があり、十分な被害回復が図られているとは言い難い状況でした。そこで、消費者を保護することを目的として、平成13年4月に消費者契約法が施行されました。この法律によると、事業者が消費者に対して、たとえば不適切な契約勧誘を行って消費者が事実を誤認したり、またその勧誘行為により消費者が困惑して契約した場合等、従来の枠組みからすれば契約の取消や解除が困難な場合でも、消費者はこの契約の取消が可能となります(消費者契約法4条)。また、仮に消費者にとって不利で、事業者にとって有利な条項(例えば事業者の損害賠償責任の免除)が契約に盛り込まれていたとしても、その条項は無効となる可能性もあります(消費者契約法8~10条)。
さらに、訪問販売・電話勧誘販売等、特定商取引法など各種の特別法の定めるクーリング・オフや中途解約権は、この法律に定める取消権とは別個の制度(割賦販売法・特定商取引法)であるので、消費者はそれぞれの要件が備わっていれば、これらの権利を別々に行使することができます。
そこで、具体的な取引行為の態様に応じて、これら消費者保護の諸法律に定められた権利を行使して、被害を回復してゆくことになります。
~製造物責任~
一般に、消費者が製品を購入する場合、当該製品は製造メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーたる消費者の手に渡るという経路をとります。この場合、消費者の立場からすれば、小売店が直接の取引相手となるわけですから、契約関係はこの小売店との間にのみ存在し、製品の製造メーカーと直接の契約関係がない以上、製品に不具合が生じたり、あるいはその製品を使用していたら怪我をしてしまった場合でも、小売店に対してしか責任追求がなし得ないことになりかねません。
そこで、製造物責任法は、例えば製造物に欠陥があり消費者の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できると規定し、これにより消費者の被害回復を図ろうとしています。
もっとも、一口に製品の「欠陥」といっても、どの程度の不具合がこれに該当するのかは個々の製品の形状・性質・利用方法等の諸条件により異なります。また、本法による損害賠償請求権は、損害及び賠償義務者を「知った時から3年」(または製造物の引渡をうけた時から10年)で時効消滅してしまうことから、その点の注意は必要です。
不動産事件
不動産とは、簡単に言えば土地や建物のことで(民法では土地及びその定着物と定義されています)、不動産に関する事件は、この不動産を買ったり売ったりする取引に関連して生じるものや、貸し借りについて生じるもの(→借地借家の問題となります)が主になります。そして、不動産については登記制度が取られていますので、この登記についての問題も生じ得ます。不動産を買ったのにその不動産に人が住んでいて出て行ってくれない場合や、賃貸借契約が終了したから賃借人を追い出したい場合などには、まずは内容証明等を使って交渉によって明渡(引渡)を要求し、それがダメであれば訴訟によってこれを請求することになります。
この場合には、明渡(引渡)を請求する方が、その請求に理由があること(たとえば自分がきちんとした取引によって所有者になったことや、賃貸借契約が解除されたことなど)を主張・立証することになります。これに対して、不動産に居続ける側が、自分が居続けることに正当な理由があること(たとえばその不動産の所有権を自分が取得していることや、賃貸借契約が有効に続いていることなど)を反論することになります。
不動産の事件は、その規模・価格が大きいことや価値の算定が難しいこと、借地借家法などの適用があること、登記制度によりその登記の先後関係が重要な意味を持つことなどから、しっかりした調査や弁護士などの専門家によるアドバイスが不可欠な事例と言えます。
また、裁判に勝ったとしても、実際に相手を強制退去させて不動産を自分の管理下に置かなくては最終的な解決とは言えず、このためには強制執行の手続きを取る必要がありますが、執行の手続は非常に複雑ですので、これも弁護士などの専門家に依頼するのが安全です。
各種書面作成及び示談交渉、内容証明、契約締結交渉
~各種書面作成~①各種契約書・契約書作成
最近では各人の権利意識の高揚のためか、中小規模の会社や自然人間でも、後日の紛争予防のため、予め各種契約書を交わしておくことも珍しくなくなりました。
我々弁護士が日常業務を行っていると、しばしば「あのときの約束をきちっと形に残していればよかった」「長年のつき合いがあるから、わざわざ書面をつくることまでしなかった」という類の話を耳にすることがあります。
不動産の売買・賃貸、金銭消費貸借、雇用、請負、委任、労働等典型契約の各契約書から、無名契約の契約書まで、それぞれの契約の特性に従った内容の契約書を交わさないと、せっかく作成した契約書であっても効力が生じず、結局紛争となってしまう場合もあります。
そこで、後日紛争が起きるリスクを少しでも防止するために、適切な形式の契約書を交わしておくことが有益となるのです。
②内容証明・内容証明郵便
何か紛争が生じた場合、当事者としては、相手方に対し、例えば、契約書の内容に添った履行を促したり、更には契約の解除をしなければならない場合があります。あるいは、先ず損害賠償の請求の意思表示をキチンとしておかなければならない等の場面を迎えます。こうした場合、当事者の意思表示が、何時、どの様な内容で相手方になされたのかということが後々大変重要な問題になってきます。こうした重要な意思表示を証拠として保全しておくことができるように、内容証明郵便という方法が使用されています。
また内容証明郵便は、送り主が出した手紙と全く同じ内容の文書を郵政省が保存するため(「内容証明の取扱いにおいては、郵政省において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する」郵政法第63条)、後日同様の文書を受け取っていないという相手方の反論を許さないという効果があります。
配達記録付にした内容証明郵便は、当該文書を特定日に出し、それが相手に到達したことの証拠となり、また文書に確定日付を与える効果もあります。
実際上、相手方との交渉の第一歩として、送り主の意向を伝えるという重要な役割を果たします。また、内容に限定があるわけではなく、あらゆる種類の交渉の第一歩と言っても過言ではありません。
もっとも、送った文書の内容が正しいのかどうかという点については、内容証明郵便で証明できるわけではないので、その点は注意が必要です。
~示談・契約締結交渉~
通常、なんらかのトラブルを抱えてしまった場合、いきなり裁判所に訴訟を持ち込むあるいは持ち込まれるのは、むしろ希なケースです。というのも、実際、裁判所以外での解決、即ち示談交渉等で事件が解決してしまう場合も相当あるからです。もっとも、当事者同士で交渉している場合、どうしても感情的になったり、事案に応じた社会的相場が分からなかったりして、なかなか解決まで至らないということもよくあります。
また、各種契約をこれから締結しょうという場合、具体的な契約条項について、後日どのような場合に不利となり、逆にこのような条項を入れられれば有利になるかという知識を持って交渉に臨む事も、事業活動には不可欠となります。
境界に関する訴訟
これは、接する土地の間の境界線はいったいどこなのかという訴訟です。公図、測量図、分筆図面等の図面類、その他表示登記の経緯、土地の形状、高低、道路位置等々のあらゆる情報を総合的に検討して何が最も合理的なのかを検討して裁判所が判決をもって境界線を決することになっています。
保全命令事件
裁判を起こす場合、判決までの間に一定の期間がかかることが予想されますが、こうした場合、判決までに現状を変えられてしまっては意味がなくなるという時にあらかじめ保全命令を受けておくことが考えられます。例えば、貸し金請求や損害賠償請求をする場合、先にその所有不動産を仮差押をするなどの例です。これは判決までにめぼしい財産を処分されては困るので仮に、判決の結果が出るまで一時的に差押えをしておくというものです。
また、明渡請求訴訟をする場合など判決が出るまでに占有屋などという人間に物件を移転され占拠されても困ります。こうした場合は、占有移転禁止仮処分をかけることになります。このような保全命令の内容は非常に多岐にわたります。
こうした保全処分をするには、判決が確定する前に相手の財産に一定の処分をするわけですから、裁判所が命ずる保証金を供託する必要があります。
訴訟を提起する前に保全処分をする必要があるケースか否か十分検討する必要があります。
民事執行事件
判決が確定しても相手がその判決どおりに実行しなければ判決は画餅に帰します。こうした場合、判決を強制的に実現することが民事執行です。
お金を返しなさいという判決を得ても、実際には返してもらえない場合、相手の預貯金、給料の差押え、不動産の差押えなどを実行する必要があります。
また判決によっては、建物の明渡しを命ずるものもあります。こうした場合は、相手を建物から強制的に立ち退かせる明渡断行を執行することになります。
さらには建物収去土地明渡請求訴訟の判決は、建物を取り壊して土地の明渡しを命じています。従ってこうした判決を実現するには実際に建物を取り壊す執行を行わなくてはなりません。
このように判決によって民事執行の方法が異なります。どういう執行を選択するかは十分検討する必要があります。